なぜメンタルケア面談が必要なのか?労災認定増加の背景と企業リスク
2025.08.27
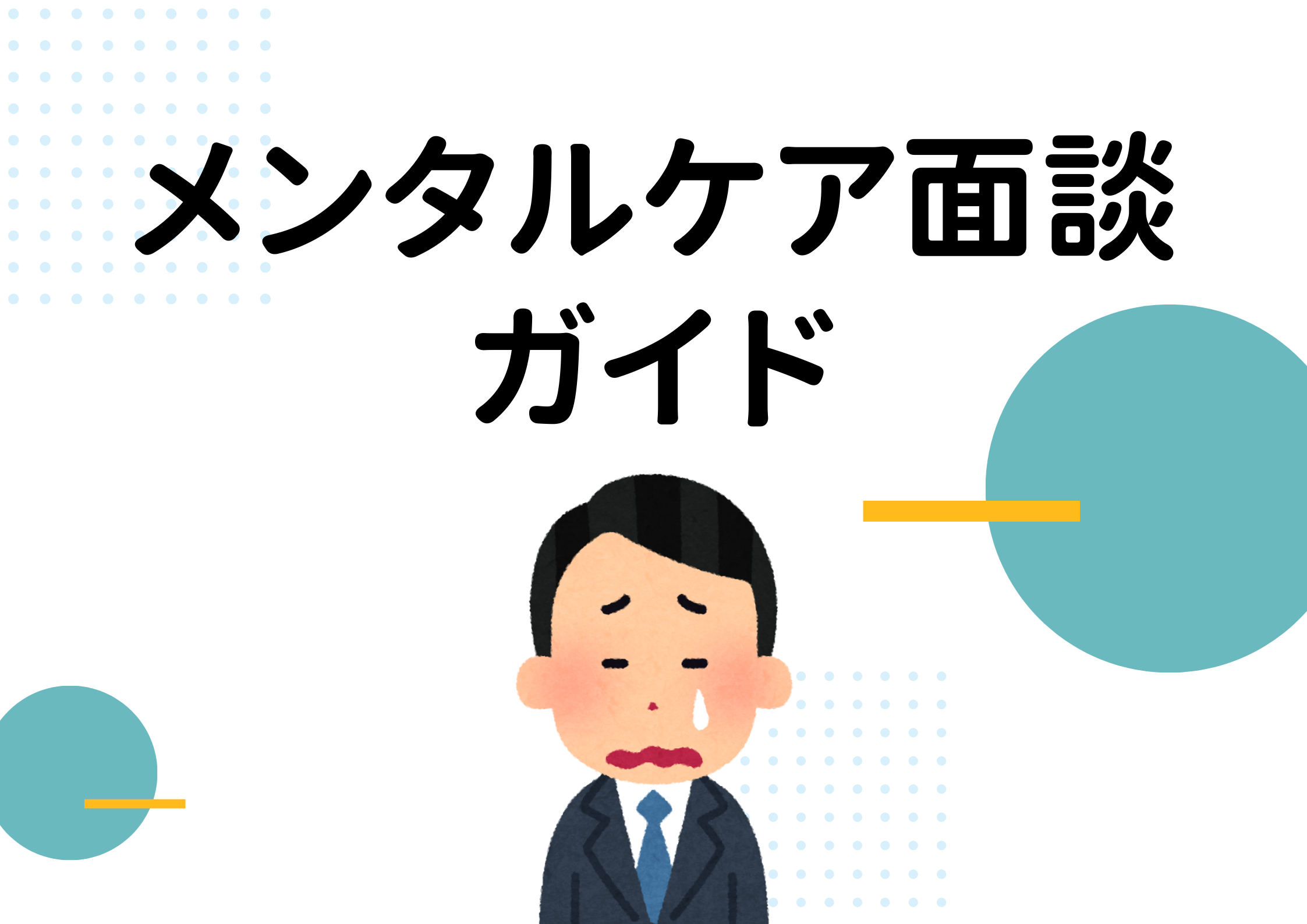
企業のメンタルケア面談の重要性や具体的な方法について解説します。
動画で学びたい方は以下をご覧ください。
https://pdca-school.jp/download-file/mentaru
メンタルケア面談の重要性と背景
近年、精神疾患による労災認定が著しく増加しており、従業員の「心の健康管理」は企業にとって喫緊の課題となっています。厚生労働省の発表によると、精神障害による労災認定件数は2013年度の約400件から2022年度には710件に増加しています 。また、1ヶ月以上の休業を要するメンタル不調者の割合は8.8%に上ります。
しかし、現在の企業のメンタルヘルス対策は、ストレスチェックの実施や相談窓口の設置といった形式的なものが多く、実質的な効果を上げられていないのが現状です。対策に取り組む企業は約6割に上るものの、「相談窓口を設置しているだけで、その後のフォローがない」といった形骸化が浮き彫りになっています。
メンタル不調に陥ると、従業員は消極的になったり、自己嫌悪や罪悪感に苛まれたり、あるいは怒りとなって反発し、最終的には離職や休業といった形で会社に大きな損失をもたらす可能性があります。
理想的なメンタルケア面談の実施体制

メンタルケア面談は、直属の上司が担当するよりも、人事担当者や他部署の先輩・上司など、直属の上司ではない第三者が担当することが望ましいとされています。これにより、従業員は普段上司に言えない本音や愚痴を吐き出しやすくなり、より深い課題を把握することが可能になります。
また、面談内容は直属の上司を含む一切の他者に他言しないという約束が必須であり、これを遵守することが信頼関係を築く上で極めて重要です。最も重要なのは、2か月に1回、毎月1回など、決まった頻度で定期的に面談を開催することです。これにより、従業員は「また話せる場があるから、今週は乗り越えよう」と前向きに捉え、頑張れるようになります。
面談の4つのコツ

受け止めるが賛同はしない
従業員が会社への不満や愚痴をこぼした際、「そう受け取っているんだね」「そう感じているんだね」と、相手の気持ちを受け止める姿勢は重要です。しかし、「ひどいよね」のように発言内容に賛同することは避けるべきです。賛同してしまうと、相手のネガティブな思考を肯定することになり、視点を変える機会を失わせてしまいます。
一切否定しない
「会社のこういう所がおかしいと思う」といった意見に対して、「良いところもあるよ」と頭ごなしに否定することはせず、まずは「共感や受け止め表現」を用いることが重要です [cite: 63]。相手の言葉から汲み取れる感情(「辛いよね」「イライラするよね」「嬉しいですよね」など)を返してあげることで、寄り添う姿勢を示します。」
共感と受け止め表現
上記2つのコツと関連しますが、相手の感情に寄り添い、共感を示す表現を用いることが、従業員の安心感につながります。
バックトラッキングの活用
相手の言ったことを繰り返したり、要約して確認したりする「バックトラッキング」のスキルは、相手に「きちんと話を聞いてもらえている」という安心感を与え、理解を深める上で非常に有効です。
面談の流れとトーク例

面談の最終的な目標は、従業員自身が状況を改善するための「自責的行動」を引き出すことです。面談は単に話を聞くだけでなく、従業員が前向きな行動へ繋がるきっかけを提供する場としましょう。
具体的な面談の流れは以下のステップで進めます 。
1.現在のモチベーションやメンタルの状況を自己採点してもらう。
2.減点されている理由や状況・シチュエーションを尋ね、感情を察する。
3.どのような環境や状態になると改善できるか、解決策を探る。
4.改善するために自らとるべき行動は何かを確認し、自責的行動を促す。
5.必要な協力やサポートを確認する。
6.加点できている状況やシチュエーションを確認する。
7.減点があったとしても、何がもっとやる気を起こさせるか(指南やリクエスト)を確認する。
例えば、従業員が「課長の指示が雑なせいで業務がなかなか進まない」と訴えた場合、面談担当者は「そう受け取っているんだね」「そう感じているんだね」と気持ちを受け止めつつ、「ひどいよね」のように発言内容に賛同することは避けるべきです。
また、「なんで新人が電話を取るんですか?一番知識ないのに、、、」といった意見に対しては、「良いところもあるよ」と否定せず、「辛いよね」「イライラするよね」といった共感や受け止め表現を用いることが重要です。
従業員が「先週、請求書作成を教わったので今週はひとりでやってみたら、、」と話した場合、「今週ひとりでやってみたんだね」と繰り返す「バックトラッキング」を用いることで、相手に話を聞いてもらえている安心感を与え、理解を深めることができます。
メンタルケア面談と通常の定期面談の2本立て
「通常の定期面談」と、人事などが担当する「メンタルケア面談」の2本立てが理想的です [cite: 83]。これにより、会社全体のコミュニケーション量が確保され、組織の活性化につながります。密なコミュニケーションが図れる組織は、結果的に従業員のエンゲージメントを高めることになります。
ケア面談だけでは解決できない課題と根本解決

メンタルケア面談だけでは、同じ問題が繰り返し出てくる、社員の悩みの根本原因が上司のマネジメント不足にある、面談で課題は把握できるが現場での解決に至らない、管理職によって部下育成力にばらつきがある、といった課題が解決できない場合があります。
これらの課題を根本的に解決するには、現場の管理職のマネジメント力向上が不可欠です。面談と管理職研修を組み合わせることで、より効果的な人材育成が実現できます。PDCAの学校では、管理職の行動が変わり、効果が実感できる「現場マネジメント研修」を提供しており、研修を3日~6日間実施し、目標管理ツールを使用し、研修で学んだことを実践する場を設けるなど、実践的な内容となっています。
- 株式会社PDCAの学校/
- コラム /
- なぜメンタルケア面談が必要なのか?労災認定増加の背景と企業リスク
無料で学べる全4章
Eラーニング「新入社員研修」
ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる
- 第一章
- 超実践!ビジネスマナー
- 第二章
- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)
- 第三章
- 絶対関係構築!コミュニケーション
- 第四章
- クレームをファンに変える!顧客対応
-
CONTACT研修のご相談はこちら
設立以来15年間で延べ
5000社以上110,155名の支援実績 -
RECRUIT採用情報
一人一人の価値を圧倒的に高める
「働きがいを生きがいへ」



