報連相できない部下の原因と、効果的な改善策7選
2025.04.28
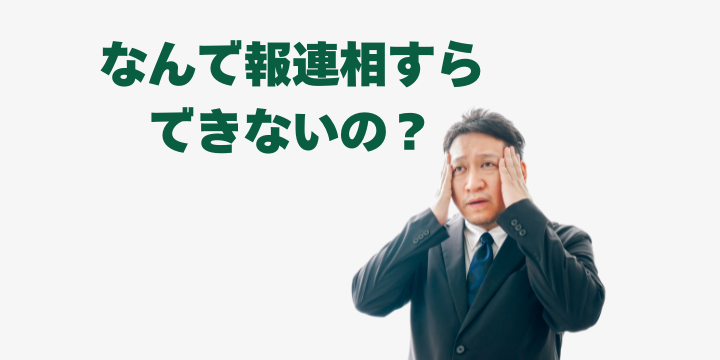
ビジネスにおいて「報告・連絡・相談」、いわゆる「報連相」は組織運営の基本中の基本です。
しかし、多くの企業で「報連相できない部下」の問題に頭を悩ませている管理職は少なくありません。報連相が適切に行われないことで、プロジェクトの遅延、顧客対応の齟齬、チーム内の不和など、さまざまな問題が生じています。
本記事では、報連相できない部下の原因を深く掘り下げ、効果的な改善策を提案します。
報連相できない原因パターン分析
報連相ができない原因は一様ではなく、パターンに分類できます。それぞれの原因を理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。
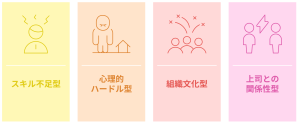
スキル不足型

単純に「どう報連相すべきか」を知らないケースです。
新入社員や若手社員に多く見られ、以下のような特徴があります。
< 特 徴 >
・何を報告すべきか、判断基準がわからない
・情報の優先順位づけができない
・ビジネス文書やメールの書き方に不慣れ
・口頭でのコミュニケーションスキルが未熟
これは最も対応しやすい原因であり、適切なティーチングで改善が期待できます。本人に方法やミスの原因を考えさせるようなコーチング要素は除外することをおすすめします。
心理的ハードル型

スキルはあっても、心理的な理由から報連相ができないパターンです。
当人の性格特性の問題もありますが、心理的安全性の低い職場では起こりやすく、特にミスが怪我につながるような現場系でよく見られます。
< 特 徴 >
・失敗や問題を報告することへの恐怖
・自分で解決すべきという過度なプレッシャー
・質問や相談をすることで無能に見られるのではないかという不安
・完璧主義による報告のタイミングを逃す傾向
このタイプは、組織の心理的安全性を高め、コミュニケーションを促進する文化づくりが重要です。
組織文化型
 組織もしくは所属チーム自体に「報連相をしなくていいと思わせる文化」が存在するケースです。
組織もしくは所属チーム自体に「報連相をしなくていいと思わせる文化」が存在するケースです。
< 特 徴 >
・報連相しなくても問題ないという暗黙の了解
・過去に報連相したことで否定的なフィードバックを受けた経験
・自立していることと報連相しないことを混同
・忙しさを理由にコミュニケーションが後回しになる風土
このパターンは個人の問題ではなく、組織文化の変革が必要です。
上司との関係性型
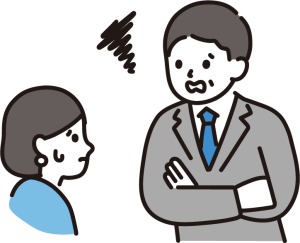
上司と部下の関係性に起因する報連相の不足も見られます。
< 特 徴 >
・上司が忙しそうで声をかけづらい
・上司のコミュニケーションスタイルと部下のスタイルがミスマッチ
・過去に報連相した際の上司の反応が否定的だったことがある
・上司自身が報連相の重要性を正しく認識できていない
この場合、上司自身の意識改革と行動変容が求められます。
報連相できない部下への効果的な改善策
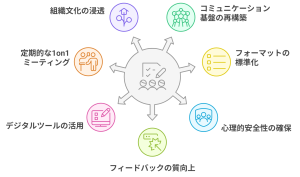
原因分析を踏まえ、報連相できない部下に対する効果的な改善策を7つご紹介します。
改善策1: コミュニケーション基盤の再構築
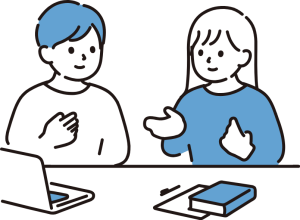
報連相の前提となるのは、円滑なコミュニケーションが可能な環境です。まずは基盤から見直しましょう。
実践ポイント
✅ 報連相の目的と意義を組織全体で再確認する機会を設ける
✅ 各チームや部署の特性に合わせた報連相ガイドラインを作成
✅ 新入社員研修に報連相の実践的トレーニングを組み込む
✅ 定期的な報連相スキルアップセミナーを開催
一般的に、報連相の重要性を理解していても「どのレベルの情報を、いつ、どのように共有すべきか」の具体的な基準が不明確なケースが多いです。明確なガイドラインを設けることで、部下の迷いを減らすことができます。
改善策2: 報連相のフォーマット標準化

報連相のハードルを下げるには、シンプルで使いやすいフォーマットの標準化が効果的です。
実践ポイント
✅ 日報・週報テンプレートの最適化
✅ 報告すべき事項のチェックリスト作成
✅ 緊急度に応じた報告方法の明確化(メール、チャット、直接対話など)
✅ 会議の目的と議事録フォーマットの標準化
特に若手社員や報連相に不慣れな社員にとって、フォーマットが明確になることで「何をどう伝えればよいか」の悩みが解消され、報連相の質と量が向上します。
改善策3: 心理的安全性の確保

報連相できない大きな要因の一つが「報告することへの恐れ」です。特に問題や失敗の報告には心理的なハードルが存在します。
実践ポイント
✅ 「早期報告は評価される」という価値観の浸透
✅ 失敗を非難せず、解決策を一緒に考える姿勢を示す
✅ 相談しやすい雰囲気づくり(定期的なカジュアルな対話の機会など)
✅ 報連相に対する肯定的なフィードバックの徹底
心理的安全性が確保された環境では、部下は失敗や問題も含めて積極的に報連相できるようになります。これにより、問題の早期発見・対応が可能になり、組織全体のリスク管理能力が向上します。
改善策4: フィードバックの質向上

部下の報連相に対するフィードバックの質が、その後の行動に大きく影響します。
実践ポイント
✅ 具体的で建設的なフィードバックを心がける
✅ 良い報連相の事例を積極的に評価し、共有する
✅ 報連相の改善点を明確に伝え、次へのアクションにつなげる
✅ フィードバックは内容だけでなくタイミングにも配慮する
「報告してもフィードバックがない」「報告しても否定されるだけ」という経験が、報連相を避ける行動につながります。適切なフィードバックにより、部下は「報連相する価値がある」と実感できるようになります。
改善策5: デジタルツールの活用
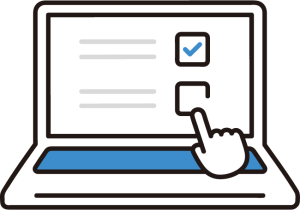
現代のビジネス環境では、デジタルツールを効果的に活用することが報連相の質と効率を高めます。
実践ポイント
✅ ビジネスチャットツールの導入と運用ルールの明確化
✅ プロジェクト管理ツールでの進捗共有の習慣化
✅ クラウドドキュメントを活用した情報の一元管理
✅ オンラインミーティングの効率化とルール設定
特に、リモートワークやハイブリッドワークが普及した現在、適切なツールの選定と利用ルールの確立は欠かせません。ただし、ツールの導入自体が目的化しないよう注意が必要です。
改善策6: 1on1ミーティングの定期実施

定期的な1on1ミーティングは、報連相を促進するための重要な機会です。
実践ポイント
✅ 週1回など定期的なスケジュールの確保
✅ オープンエンドな質問でコミュニケーションを促す
✅ 業務課題だけでなく、キャリアや成長についても対話
✅ ミーティングの主導権を部下に持たせる工夫
1on1ミーティングでは、単なる業務報告だけでなく、部下の悩みや課題、アイデアなども引き出すことができます。また、上司と部下の信頼関係構築にも役立ち、日常的な報連相のハードルを下げる効果があります。
改善策7: 組織文化としての報連相の価値浸透

最終的に目指すべきは、報連相が当たり前に行われる組織文化の醸成です。
実践ポイント
✅ 経営層や管理職が報連相の模範を示す
✅ 報連相の優れた事例を表彰する制度導入
✅ 部門を超えた情報共有の機会を定期的に設ける
✅ 報連相の質と量を人事評価の一要素に組み込む
組織文化の変革には時間がかかりますが、継続的な取り組みにより、「この組織では報連相は当然のこと」という認識が浸透していきます。特に管理職の行動が重要であり、彼らが率先して報連相の価値を体現することが必要です。
報連相を徹底させるマネジメント方法は
無料公開動画(30分)で詳しく解説しておりますので是非ご視聴ください!
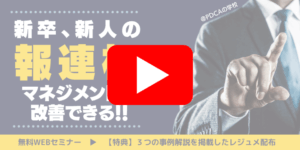
まとめ:持続可能な報連相環境の構築へ
報連相できない部下の問題は、個人の資質だけでなく、組織の環境や文化にも大きく影響されます。
本記事で紹介した7つの改善策は、それぞれの組織の状況に合わせてカスタマイズし、組み合わせて活用することで効果を発揮するでしょう。
重要なのは、報連相を「強制される義務」ではなく、「組織の一員として当然の行動」と認識してもらうことです。そのためには、単なるルール化やペナルティではなく、報連相がもたらす価値を実感できる仕組みづくりが欠かせません。
報連相できない部下の改善には、根気強い取り組みが必要ですが、その先に待っているのは、風通しの良い強靭な組織です。
今日から、できることから始めてみませんか。
組織風土を変えていく『フォロワーシップ』ご存じですか?
- 株式会社PDCAの学校/
- コラム /
- 報連相できない部下の原因と、効果的な改善策7選
無料で学べる全4章
Eラーニング「新入社員研修」
ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる
- 第一章
- 超実践!ビジネスマナー
- 第二章
- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)
- 第三章
- 絶対関係構築!コミュニケーション
- 第四章
- クレームをファンに変える!顧客対応
-
CONTACT研修のご相談はこちら
設立以来15年間で延べ
5000社以上110,155名の支援実績 -
RECRUIT採用情報
一人一人の価値を圧倒的に高める
「働きがいを生きがいへ」



