研修効果が続くフォローアップ体制の事例|成功企業の実践法
2025.08.21
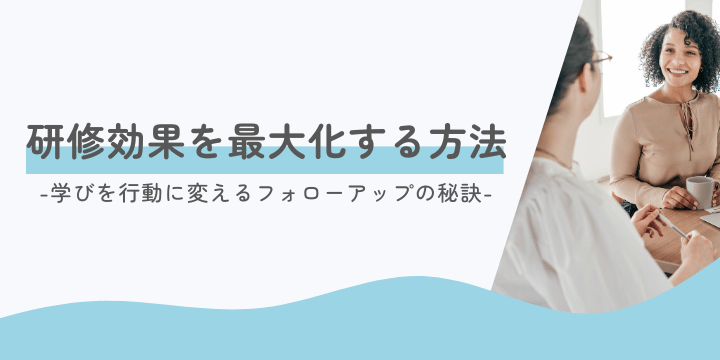
はじめに:研修効果が続くフォローアップ体制の重要性
企業が社員研修に投資する目的は、業績向上や人材育成にあります。しかし、せっかく実施した研修も、その後のフォローアップが不十分だと効果は一時的なものになりがちです。研修効果が続くフォローアップ体制の構築は、研修投資を最大化するための重要な取り組みといえるでしょう。
研修後のフォローアップが必要な理由
認知心理学の研究では、エビングハウスの忘却曲線として知られる現象があり、新しく学んだ情報は時間の経過とともに急速に忘れられていくことが示されています。研修後の定期的な復習と実践的な活用機会がなければ、投資した研修効果の大部分が失われてしまう可能性があります。実際に、多くの企業では、研修内容の実務活用に課題があり、組織的なフォローアップ体制が研修効果を持続させる重要な要素となっています。
フォローアップがない場合の問題点
✖ 研修で得た知識やスキルが定着せず、業務改善につながらない
新しく学んだスキルは、実践と反復なしには急速に忘れられていきます。実務への応用機会がなければ、学んだ内容は抽象的な知識のままで、具体的な成果につながりません。
✖ 研修への投資対効果が低下する
研修にかかるコストは、講師料、会場費だけでなく、社員の業務時間の機会損失も含めると相当な金額になります。フォローアップなしでは、この投資が十分な成果を生み出せません。
✖ 社員のモチベーション低下につながる
研修への参加が単なる「イベント」で終わり、実務に活かされないと、社員は研修自体の価値を疑問視するようになります。「学んでも変わらない」という認識が広がると、将来の研修への意欲も低下し、成長意欲の高い人材の不満や離職リスクを高める可能性もあります。
フォローアップ体制の基本要素

研修効果が続くフォローアップ体制には、以下のような重要な要素があります。
定期的な振り返りと上司のサポート
研修内容を定期的に振り返る機会を設けることで、学びを定着させます。
– 研修直後(1〜3日後)の「短時間の復習」で、重要ポイントを再確認
– 研修1週間後の「振り返りミーティング」で、実践での疑問点や課題を共有
– 研修1ヶ月後の「アクションプラン報告会」で、実践状況と成果を確認
– 研修3ヶ月後の「定着度チェック」で、持続的な活用状況を評価
また、直属の上司が研修内容を理解し、部下の実践をサポートする体制も重要です。
– 研修内容に関する事前説明会を受け、部下が学ぶ内容を理解する
– 部下の研修後アクションプラン作成をサポートし、実践機会を提供する
– 定期的な1on1ミーティングで進捗を確認し、必要なフィードバックを提供する
– 部下の成功事例を評価し、組織内で共有する機会を作る
実践の場の提供方法
研修で学んだことを実践できる機会を意図的に作ることも、フォローアップ体制の重要な要素です。
– 小規模プロジェクトへの参加機会の提供
– 内容に関する業務タスクの優先的な割り当て
– 研修内容実践タイムとして勤務時間を一部確保
– メンターやコーチとのペアワークで実践サポート
研修効果を測定する指標

フォローアップの効果を測定するためには、適切な指標の設定が必要です。総合的な評価のために、以下の指標を組み合わせて活用しましょう。
行動と業績の変化
研修前後での行動や業務プロセスの変化を観察・記録することは重要な指標となります。
– 研修内容に関連する特定行動の頻度変化(例:提案回数、顧客接点数)
– 360度フィードバックで行動変化の多角的に評価
– 業務プロセスの変更点とその定着度
また、売上や生産性などの数値的な変化を継続的に測定することで、研修の実務への効果を把握できます。
– 研修内容に関連する業務KPIの変化(売上、コスト削減、顧客満足度など)
– プロジェクト完了時間や品質指標の変化
– エラー率や再作業率の低減
知識定着度と自己評価
定期的な知識確認テストや実践状況の確認を行うことで、学びの定着度を測定できます。
– 研修内容に関する定期的な小テストやクイズ
– 実務でのスキル適用状況のチェックリスト評価
– ケーススタディを用いた応用力テスト
さらに、研修内容の活用度合いに関する自己評価も有効な指標です。
– 学んだ内容の有用性評価(5段階評価など)
– 実務での活用頻度と活用シーンの自己報告
– 研修前後でのスキル自己評価の変化
これらの指標を組み合わせることで、研修効果が続くフォローアップ体制の実効性を客観的に評価できます。
研修効果が続くフォローアップ体制の事例

富士フイルム株式会社の取り組み
富士フイルム株式会社では、社員の学びのプラットフォームである「+STORYアカデミー」を設立し、独自のフォローアップ体制を構築しています。富士フイルムのキャリアサイトによれば、同社では研修後に以下のようなフォローアップを実施しています。
✅ OJTと連携した育成支援
研修で学んだ内容を現場で実践できるよう、研修プログラムとOJTを効果的に連携させる体制を整備
✅ 先輩社員による継続的なフォロー
特に入社3年目までの若手社員に対しては、先輩社員が育成担当としてしっかりとフォローする体制を構築
✅ 自己啓発支援制度
研修後も継続的に学びを深められるよう、多様な自己啓発支援プログラムを提供
この結果、富士フイルムでは若手社員の成長が加速し、新しい事業領域への対応力が向上していると報告されています。
トヨタ自動車株式会社の取り組み
トヨタ自動車株式会社では、「モノづくりは人づくり」の理念のもと、研修効果を持続させるための独自のフォローアップ体制を構築しています。トヨタの人材育成プログラムには以下のような特徴があります。
✅ 基礎固め徹底プログラム
入社時の研修期間を1年に延長し、座学だけでなく販売店や工場での実習を含む実践的教育を提供。研修後も現場での学びを継続させる体制を整備
✅ 現場教育(OJT)と研修(Off-JT)の連携
研修で学んだ内容を実践する場を意図的に設け、上司や先輩による継続的なフォローアップを実施
✅ 定期的なフォロー教育
配属後も毎月のペースで定期的なフォロー教育を実施し、現場での実践を通じて生まれた疑問の解消や更なる技術・知識の向上を促進
これらの取り組みにより、トヨタでは「教え教えられる風土」が定着し、技術や知識の伝承が効果的に行われるとともに、自律的な改善活動が継続される現場づくりに成功しています。
効果的なフォローアップ体制構築のポイント

富士フイルムとトヨタ自動車の事例から、研修効果が続くフォローアップ体制を構築するためのポイントが見えてきます。
1. 現場と研修の連携強化
実務と研修を密接に結びつけ、学んだことをすぐに実践できる環境を整えることが重要です。トヨタの「基礎固め徹底プログラム」のように、研修と現場実習を組み合わせたプログラム設計が効果的です。
2. 先輩社員・上司の積極的関与
富士フイルムの先輩社員によるフォロー体制やトヨタの「教え教えられる風土」のように、現場の先輩社員や上司が研修内容を理解し、継続的に若手をサポートする仕組みが必要です。
3. 定期的な振り返りの機会創出
単発の研修で終わらせず、トヨタの「定期的なフォロー教育」のように、学んだ内容を実践した後の振り返りの場を設けることで、知識の定着と更なる向上を促進できます。
まとめ:持続的な研修効果を実現するために
研修効果が続くフォローアップ体制の構築は、単なる研修後のチェックリストではなく、組織文化として定着させることが重要です。富士フイルムとトヨタ自動車の事例から分かるように、効果的なフォローアップ体制には、研修と実務の連携、先輩社員や上司によるサポート体制、定期的な振り返りの機会といった要素が含まれます。
特に注目すべきは、富士フイルムの「+STORYアカデミー」やトヨタの「モノづくりは人づくり」の理念に基づく継続的な育成体制です。これらの企業では、研修を単発のイベントではなく、長期的な成長を支える仕組みとして位置づけています。
研修効果が続くフォローアップ体制を整えることで、研修投資の効果を最大化し、持続的な組織成長につなげることができるでしょう。
人材育成のフレームワークについてはこちらをご参考ください。
⇒記事:https://pdca-school.jp/column/3246
- 株式会社PDCAの学校/
- コラム /
- 研修効果が続くフォローアップ体制の事例|成功企業の実践法
無料で学べる全4章
Eラーニング「新入社員研修」
ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる
- 第一章
- 超実践!ビジネスマナー
- 第二章
- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)
- 第三章
- 絶対関係構築!コミュニケーション
- 第四章
- クレームをファンに変える!顧客対応
-
CONTACT研修のご相談はこちら
設立以来15年間で延べ
5000社以上110,155名の支援実績 -
RECRUIT採用情報
一人一人の価値を圧倒的に高める
「働きがいを生きがいへ」



