高市首相の発言で再燃!ワークライフバランスはもう古い?
2025.10.08

目次
ワークライフバランスを巡る議論が再燃
自民党の新総裁に選出された高市早苗氏の「ワークライフバランスという言葉を捨てる」という発言が、改めてワークライフバランスについて考えるきっかけとなっています。「働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」という強い決意表明は賛否両論を呼び、SNSでも活発な議論が交わされました。
中小企業の人事担当者として、この発言をどう受け止めるべきでしょうか。実は、この議論は「ワークライフバランスからワークライフインテグレーションへ」という働き方のパラダイムシフトを考える絶好の機会なのです。
本コラムでは、なぜワークライフバランスが「古い」と言われるのか、そしてこれからの時代に求められるワークライフインテグレーションの考え方と実践方法について解説します。
ワークライフバランスの限界
結論から言えば、ワークライフバランスという概念は時代にそぐわなくなりつつあります。
ワークライフバランスは「仕事とプライベートのバランスを調整して豊かに暮らす」という考え方です。内閣府も「仕事と生活の調和」として推進してきました。
しかし、この考え方には大きな問題があります。それは、仕事とプライベートを対立するもの、トレードオフの関係として捉えている点です。「子供を迎えに行くから仕事を早く終わらせる」「仕事を成功させたいからプライベートの時間を削る」——このように、どちらかを優先すれば、もう片方が犠牲になるという前提に立っています。
仕事を重視すれば家庭が疎かになり、家庭を優先すればキャリアを諦める。この二律背反の構造が、多くの働く人を悩ませてきたのです。
ワークライフインテグレーションという新しい考え方
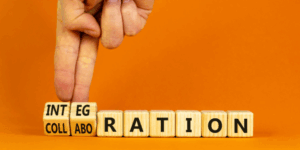
そこで注目されているのが、ワークライフインテグレーションです。
ワークライフインテグレーションとは、仕事とプライベートを統合し、双方を充実させることで相乗効果を生み出す考え方です。2008年に経済同友会が提唱し、慶應義塾大学の高橋俊介教授らによって広められました。
両者の決定的な違い
ワークライフバランスは、仕事とプライベートを分離して考える概念です。どちらかを優先すれば、もう一方が犠牲になるという前提に立ち、両者のバランスを調整することで「妥協の産物」を生み出します。あくまで時間配分の問題として捉え、「今日は残業するから家族との時間が減る」「来週は休暇を取るから仕事を前倒しする」といった調整を繰り返すのです。
ワークライフインテグレーションは、仕事とプライベートを統合して考えます。両者が対立するのではなく、互いに高め合う関係を構築し、相乗効果による「価値の最大化」を目指します。人生全体の質の問題として捉え、時間の奪い合いではなく、双方の充実による好循環を追求するのです。
つまり、ワークライフインテグレーションは、仕事とプライベートの間に明確な線を引かず、「仕事が充実すればプライベートも充実する」「プライベートが豊かになれば仕事のパフォーマンスも上がる」という好循環を目指すのです。
なぜ今、ワークライフインテグレーションなのか

中小企業の人事担当者が知っておくべき背景として、3つの大きな変化があります。
> テクノロジーの進化
リモートワークやクラウドツールの普及により、物理的に仕事とプライベートの境界が曖昧になりました。自宅で仕事をし、仕事中に私用のメールを確認する——このような働き方が当たり前になった今、厳密な線引きは現実的ではありません。
> 価値観の多様化
特に若年層を中心に、「仕事は生活の一部であり、自分らしさを表現する手段」という価値観が広がっています。仕事とプライベートを切り離すのではなく、人生全体を統合的に捉える考え方が支持されています。
> 労働生産性の問題
日本の労働生産性は主要先進国で最低水準にあります。長時間働いても成果が出ない——この問題を解決するには、時間管理だけでなく、働く人の充実度そのものを高める必要があるのです。
中小企業がワークライフインテグレーションを導入するメリット
ワークライフインテグレーションの導入は、中小企業に4つの大きなメリットをもたらします。
① 採用競争力の飛躍的向上
「ワークライフバランス重視」の企業は増えましたが、「ワークライフインテグレーション実現」を掲げる企業はまだ少数です。先駆的な取り組みは、求職者、特に優秀な人材に強くアピールできます。
② 従業員エンゲージメントの向上
仕事とプライベートが好循環を生む環境では、従業員は仕事に対してより高いモチベーションと当事者意識を持つようになります。
③ イノベーションの創出
プライベートで得た経験や学びを仕事に活かし、仕事で培ったスキルをプライベートで展開する——この統合的な活動が、新しいアイデアやイノベーションを生み出します。
④ 多様な人材の活用
育児や介護、副業、学び直しなど、さまざまなライフステージやライフスタイルの人材が活躍できる環境が整います。
中小企業におけるワークライフインテグレーションの実践方法

では、具体的にどのように導入すればよいのでしょうか。
ステップ1: 経営層の意識改革
最も重要なのは、経営層が「仕事とプライベートは対立しない」という認識を持つことです。
具体的なアクション:
• 経営会議でワークライフインテグレーションの概念を共有
• 経営層自身が実践し、ロールモデルとなる
• 「長時間働く=頑張っている」という価値観を捨てる
ステップ2: 柔軟な働き方の制度化
仕事とプライベートを統合するには、時間と場所の柔軟性が不可欠です。
導入しやすい制度:
フレックスタイム制
コアタイムを設けた上で、出退勤時間を従業員が決められる制度。子供の送迎や通院、自己啓発の時間を確保しやすくなります。
リモートワーク・ハイブリッドワーク
週2〜3日は在宅勤務、残りは出社といった柔軟な働き方。通勤時間の削減は、時間的・精神的余裕を生み出します。
裁量労働制
一定の職種において、労働時間ではなく成果で評価する制度。自律的な働き方を促進します。
ワーケーション制度
休暇先で仕事をすることを認める制度。長期休暇を取りやすくなり、リフレッシュと仕事の両立が可能になります。
ステップ3: 相乗効果を生む施策の導入
単に柔軟性を高めるだけでなく、仕事とプライベートが互いに高め合う仕組みを作ります。
学び支援制度
業務に直結しなくても、本人が興味を持つ分野の学習費用を補助します。
副業・複業の解禁
他社での経験やスキルが本業にも良い影響を与えます。
家族参加型イベント
家族を職場に招くイベントを開催し、従業員の仕事への理解を深めてもらいます。
ライフイベント支援
結婚、出産、介護、子供の進学など、人生の節目を会社全体で祝い、サポートする文化を作ります。
ステップ4: 評価制度の抜本的見直し
ワークライフインテグレーションを実現するには、評価制度の変革が不可欠です。
重視すべき評価軸:
• 労働時間ではなく、成果とプロセス
• 個人の成長だけでなく、チームへの貢献
• 短期的な結果だけでなく、中長期的な価値創造
• 業務内の活動だけでなく、業務外での学びや経験の業務への還元
ステップ5: 組織文化の醸成
制度だけ作っても、使える雰囲気がなければ意味がありません。
文化醸成の具体策:
• 管理職から率先して柔軟な働き方を実践する
• 社内報やSNSで実践事例を積極的に共有する
• プライベートの充実が仕事に良い影響を与えた事例を表彰する
• 「早く帰る人=やる気がない」という空気を徹底的に排除する
ワークライフインテグレーション導入時の注意点
注意点1: 仕事の過剰な侵入を防ぐ
柔軟性が「いつでも働ける=いつでも働かされる」にならないよう、ルールを明確にします。
対策例:
• 深夜・早朝のメール送信は控える
• 休暇中の連絡は緊急時のみとする
• 「つながらない権利」を保障する
注意点2: 一律の押し付けは避ける
人によって理想的な働き方は異なります。画一的な制度ではなく、選択肢を用意することが重要です。
注意点3: 業務プロセスの見直しも並行して行う
柔軟な働き方を支えるには、業務の見える化、標準化、デジタル化が必須です。属人化した業務体制のままでは、制度が機能しません。
高市氏の発言から学ぶべきこと
高市氏の「ワークライフバランスを捨てる」発言は、一見ワークライフインテグレーションと矛盾するように見えます。しかし、実は重要な示唆を含んでいます。それは、仕事とプライベートを天秤にかけて調整するという発想自体が古いということです。高市氏は政治家として、仕事に全力を注ぐ決意を表明しました。これは「仕事を選んだ」のではなく、「政治家という仕事が自分の人生そのものである」という、まさにワークライフインテグレーションの極致とも言えます。
ただし、この働き方を一般化し、すべての人に求めることは危険です。過労死やメンタルヘルスの問題を引き起こしかねません。重要なのは、一人ひとりが自分にとって最適な仕事とプライベートの統合のあり方を選択できる環境を整えることなのです。
まとめ: 中小企業こそワークライフインテグレーションを
ワークライフバランスからワークライフインテグレーションへ——この転換は、単なる言葉の言い換えではありません。働き方に対する根本的な発想の転換です。
中小企業がワークライフインテグレーションを導入すべき理由は明確です。第一に、大企業との差別化が図れます。給与や知名度で劣っても、働き方で勝負できるのです。第二に、意思決定の速さという強みを活かせます。小回りが利き、柔軟な制度導入が可能です。第三に、経営層との距離が近いため、トップの理解さえ得られれば、組織文化の変革が早く進みます。そして第四に、持続的成長の基盤を築けます。従業員の幸福度が高い企業は、長期的に成長するのです。
仕事とプライベートを分けるのではなく、統合する。どちらかを犠牲にするのではなく、相乗効果を生み出す。バランスを取るのではなく、両方を充実させる。これがワークライフインテグレーションの本質です。「ワークライフバランスは古い」——この言葉は、二律背反の思考から脱却し、仕事もプライベートも人生の大切な一部として統合的に捉える時代が来たことを意味しています。
経営層、人事労務担当者へのメッセージ
ワークライフインテグレーションの実現は、一朝一夕にはいきません。しかし、この考え方を軸に制度設計と組織文化の醸成を進めることで、従業員一人ひとりが輝き、企業も持続的に成長する——そんな理想的な組織を作ることができます。
あなたの取り組みが、従業員の幸せと会社の未来を作るのです。まずは小さな一歩から始めてみませんか。
- 株式会社PDCAの学校/
- コラム /
- 高市首相の発言で再燃!ワークライフバランスはもう古い?
無料で学べる全4章
Eラーニング「新入社員研修」
ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる
- 第一章
- 超実践!ビジネスマナー
- 第二章
- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)
- 第三章
- 絶対関係構築!コミュニケーション
- 第四章
- クレームをファンに変える!顧客対応
-
CONTACT研修のご相談はこちら
設立以来15年間で延べ
5000社以上110,155名の支援実績 -
RECRUIT採用情報
一人一人の価値を圧倒的に高める
「働きがいを生きがいへ」




