今さら聞けないRPA化とは?人事担当者必見の業務自動化ガイド
2025.05.01
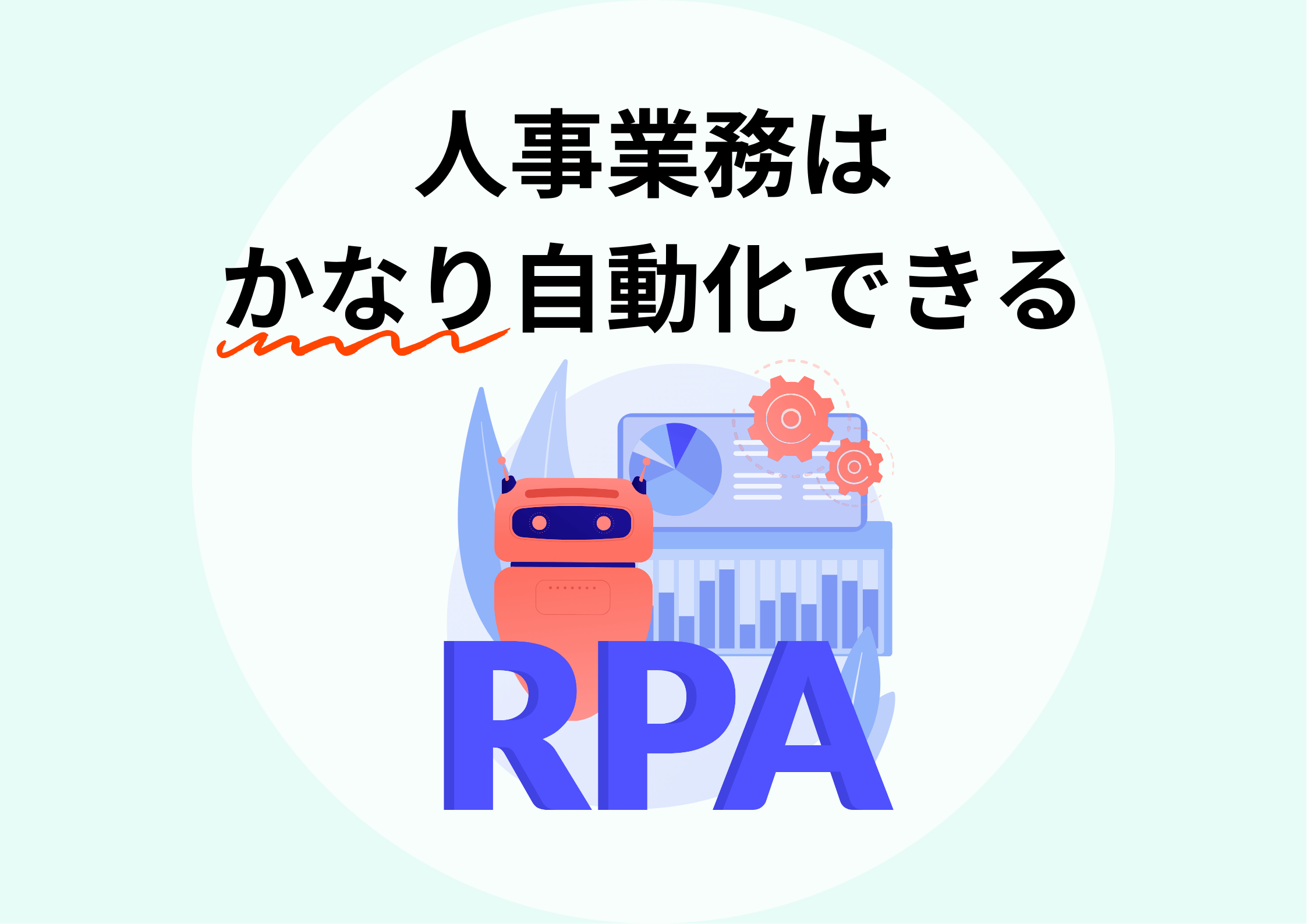
今さら聞けないRPA化とは?人事担当者必見の業務自動化完全ガイド
目次
はじめに:人事業務とRPA化の関係性
人事業務は企業運営において欠かせない重要な機能ですが、多くの定型作業や膨大なデータ処理が必要とされる領域でもあります。採用活動から退職手続きまで、さまざまな場面で発生する書類作成や情報管理は、担当者にとって大きな負担となっています。
そんな中、業務効率化の切り札として注目されているのがRPA化です。単純作業の自動化によって、人事担当者は、より戦略的な業務に集中できるようになり、企業全体の生産性向上につながります。特に中小企業においては、限られたリソースを最大限に活用する手段として、RPA化の重要性が高まっています。
RPA化とは何か:基本的な概念と人事業務への応用
RPA(Robotic Process Automation)とは、これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットが代行する技術です。具体的には、データ入力、ファイル操作、アプリケーション間のデータ転記など、決まったルールに基づく作業を自動化します。
人事業務におけるRPA化の特徴は、プログラミングの知識がなくても、視覚的な操作で自動化シナリオを作成できる点にあります。例えば、エクセルから人事システムへのデータ転記や、勤怠情報の集計といった作業が、簡単なフローチャート形式で設定可能です。
 重要なのは、RPA化は単なる業務効率化ツールではなく、人事戦略を変革する手段であるという点です。
重要なのは、RPA化は単なる業務効率化ツールではなく、人事戦略を変革する手段であるという点です。
定型業務から解放された人事担当者は、採用戦略の検討や人材育成プログラムの充実など、より付加価値の高い業務に時間を割くことができるようになります。
人事業務におけるRPA化のメリット

コスト削減と生産性向上
人事業務のRPA化によって、一般的に定型業務の処理時間は60〜80%削減されると言われています。例えば、月末の勤怠集計業務が3日かかっていたものが半日で完了するようになれば、その時間を他の戦略的業務に充てることができます。
また、24時間365日稼働できるRPAは、繁忙期の残業削減や人件費の抑制にも貢献します。中小企業では新たな人材採用が難しいケースも多いですが、RPA化によって既存の人員で業務量の増加に対応できるようになります。
ミス削減とコンプライアンス強化

人間が行う作業では、どうしてもミスが発生します。特に人事業務は個人情報を扱うことが多く、小さなミスが大きな問題につながる可能性があります。RPA化されたプロセスでは、一度正確に設定すれば、同じ作業を常に同じ品質で実行できるため、ヒューマンエラーを大幅に削減できます。
さらに、処理履歴が自動的に記録されるため、監査対応やコンプライアンスの強化にもつながります。労働法規の改正が頻繁に行われる昨今、RPAによる正確な処理は法令遵守の面でも大きなメリットをもたらします。
従業員満足度の向上

RPA化による業務効率化は、人事担当者自身の働き方にも良い影響を与えます。単調で時間のかかる作業から解放されることで、よりクリエイティブで戦略的な業務に取り組めるようになり、職務満足度が向上します。また、処理速度の向上により、従業員からの問い合わせや申請に対するレスポンスが迅速化され、社内サービスの質が向上します。例えば、休暇申請の承認や給与に関する問い合わせへの対応が早くなることで、全社的な従業員エクスペリエンスも高まります。
中小企業が人事業務のRPA化に取り組むべき理由
中小企業は大企業に比べてリソースが限られていますが、だからこそRPA化の恩恵を受けやすい側面があります。まず、導入範囲を絞りやすいため、小規模なプロジェクトからスタートできます。例えば、最も負担の大きい給与計算業務だけを最初にRPA化するといったアプローチが可能です。
また、組織の意思決定が迅速であるため、効果が出た施策を素早く展開できます。大企業では部門間の調整に時間がかかりますが、中小企業では成功事例をすぐに横展開できる機動性があります。さらに、近年ではクラウド型のRPAツールも増えており、初期投資を抑えながらRPA化に取り組むことが可能になっています。特に人事業務は、どの企業でも共通する部分が多いため、標準的なテンプレートを活用しやすく、短期間で効果を出しやすいという利点もあります。
人事業務でRPA化に適した業務領域
人事部門のすべての業務がRPA化に適しているわけではありません。最も効果を発揮するのは、定型的で繰り返し発生する作業です。具体的には以下の業務領域がRPA化に適しています。
採用業務
採用活動では、求人情報の掲載、応募者情報の管理、面接スケジュールの調整など、多くの定型業務が発生します。RPAを活用することで、複数の求人サイトへの一括投稿や、応募者データの自動集計、選考ステータスの管理などが自動化できます。
 特に効果的なのは、応募者とのコミュニケーションです。面接日程の調整や結果通知など、定型メールの送信をRPA化することで、応募者体験の向上と担当者の負担軽減を同時に実現できます。
特に効果的なのは、応募者とのコミュニケーションです。面接日程の調整や結果通知など、定型メールの送信をRPA化することで、応募者体験の向上と担当者の負担軽減を同時に実現できます。
勤怠管理

タイムカードや勤怠システムからのデータ取得、休暇申請の処理、勤怠異常の検出といった業務は、RPA化の恩恵を大きく受ける領域です。例えば、月末の勤怠集計では、システムからのデータ抽出、異常値のチェック、集計表の作成といった一連の作業を自動化できます。また、有給休暇の残日数計算や時間外労働の集計なども、RPAが得意とする業務です。
給与計算

多くの中小企業で最も負担が大きいのが給与計算業務です。勤怠データの取り込み、各種手当や控除の計算、給与明細の作成など、正確性が求められる作業が月次で発生します。RPA化によって、異なるシステム間のデータ連携がスムーズになり、計算ミスのリスクが低減します。さらに、社会保険や税金の計算など、複雑なルールに基づく処理も正確に行えるようになります。
トレーニング管理
研修の案内、参加者の管理、修了証の発行といった業務もRPA化に適しています。社内研修システムと人事データベースを連携させ、対象者への自動通知や受講履歴の自動更新などが可能になります。

また、eラーニングシステムと連動させることで、未受講者への督促や進捗状況の集計なども自動化できます。研修効果の測定や分析にかける時間を増やすことで、より質の高い人材育成が実現します。
RPA化導入のステップ・バイ・ステップガイド
現状分析と業務の可視化
RPA化を成功させる第一歩は、現状の業務プロセスを詳細に把握することです。
どの業務にどれだけの時間がかかっているのか、どのような問題が発生しているのかを明確にしましょう。

具体的には、業務フローを図式化し、各ステップの所要時間や発生頻度、関連システムなどを整理します。この過程で、単純にRPA化するのではなく、業務自体の見直しや簡素化も検討することが重要です。
ツール選定のポイント
RPA化ツールには、高機能で導入コストが高いものから、クラウド型の比較的安価なものまで、多様な選択肢があります。初期段階では、無料トライアルやPOC(概念実証)を活用して、実際の業務に適用してみることをお勧めします。
中小企業が選定する際のポイントとしては、以下の点に注目するとよいでしょう。
✅ 使いやすさ・・・・プログラミング知識がなくても、視覚的に操作できるか
✅ 拡張性・・・・・・将来的に適用範囲を広げる際に柔軟に対応できるか
✅ サポート体制・・・トラブル時のサポートや、定期的なアップデートが提供されるか
✅ 導入実績・・・・・同規模の企業や同業種での導入事例があるか
パイロット導入と効果測定
全社展開の前に、特定の業務や部門でパイロット的にRPA化を実施することが重要です。比較的シンプルで効果が出やすい業務から始めることで、早期に成功体験を得ることができます。![]()

効果測定においては、定量的な指標(作業時間、処理件数、エラー率など)と定性的な指標(担当者の満足度、ストレス軽減など)の両面から評価します。これらのデータは、次のステップへの投資判断や全社展開の説得材料として活用できます。
全社展開のためのポイント
パイロット導入の成果を全社に展開する際は、以下の点に留意することが成功のカギとなります。
経営層のコミットメント:RPA化を単なるコスト削減ではなく、戦略的な取り組みとして位置づける
担当者の育成:内部にRPA化の知識を持つ人材を育成し、持続的な推進体制を構築する
成功事例の共有:具体的な効果や実際の運用方法を社内で共有し、他部門の理解を促進する
段階的アプロー段階的アプローチ:一度にすべてを自動化するのではなく、優先度の高い業務から順次展開する
RPA化導入時の注意点と失敗しないためのヒント
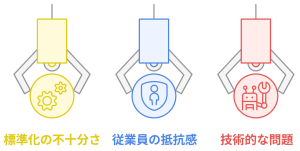
RPA化の導入プロジェクトが失敗するケースには、いくつかの共通するパターンがあります。これらを事前に認識しておくことで、リスクを軽減できます。
まず、業務プロセスの標準化が不十分なまま自動化を進めると、例外処理が多発し、かえって効率が低下する可能性があります。RPA化の前に業務の整理と標準化を行うことが重要です。
次に、現場担当者の抵抗感です。「自分の仕事が奪われる」という不安から、協力が得られないケースがあります。RPA化の目的が「単純作業からの解放」であり、より創造的な業務にシフトするためのものであることを丁寧に説明しましょう。
また、技術的な面では、システム更新や画面レイアウトの変更によって、設定したRPAシナリオが動作しなくなるリスクがあります。定期的なメンテナンスや柔軟性を持たせた設計が必要です。
未来の人事業務:RPA化の次に来るもの
RPA化は人事業務の自動化の第一歩に過ぎません。今後は、AIやデータ分析と組み合わせることで、より高度な業務支援が可能になると予想されています。例えば、採用業務では、応募者の適性を自動判定するAIや、離職リスクを予測するモデルの活用が始まっています。また、チャットボットを活用した従業員からの問い合わせ対応も広がりつつあります。

RPAで基本的な業務の効率化を達成した後は、蓄積されたデータを活用した意思決定支援や、従業員体験の向上に焦点を当てた取り組みが重要になるでしょう。人事部門は、「管理」から「戦略的パートナー」へと、その役割をさらに進化させていくことが期待されています。
まとめ:人事業務のRPA化で実現する新しい働き方

人事業務のRPA化は、単なる業務効率化の手段ではなく、企業の人事戦略そのものを変革する重要な取り組みです。定型業務の自動化によって、人事担当者はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになり、企業全体の競争力強化につながります。
特に中小企業においては、限られたリソースを最大限に活用するためのRPA化が重要です。採用、勤怠管理、給与計算、研修管理といった業務領域で積極的に自動化を進めることで、コスト削減、ミス防止、従業員満足度向上などの多面的なメリットを享受できます。
RPA化導入にあたっては、現状分析から始まり、適切なツール選定、パイロット導入、効果測定、全社展開という段階的なアプローチが重要です。また、業務の標準化や例外処理の整理、セキュリティ対策なども成功のカギとなります。
将来的には、RPAとAIやデータ分析を組み合わせることで、より高度な人事業務の自動化と意思決定支援が可能になるでしょう。今、RPA化に着手することは、未来の人事部門への重要な一歩となります。時代の変化に対応し、競争力を維持するためにも、RPA化への取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。
研修に取り入れたいeラーニングシステムをご紹介!
⇒記事 https://pdca-school.jp/column/3183
- 株式会社PDCAの学校/
- コラム /
- 今さら聞けないRPA化とは?人事担当者必見の業務自動化ガイド
無料で学べる全4章
Eラーニング「新入社員研修」
ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる
- 第一章
- 超実践!ビジネスマナー
- 第二章
- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)
- 第三章
- 絶対関係構築!コミュニケーション
- 第四章
- クレームをファンに変える!顧客対応
-
CONTACT研修のご相談はこちら
設立以来15年間で延べ
5000社以上110,155名の支援実績 -
RECRUIT採用情報
一人一人の価値を圧倒的に高める
「働きがいを生きがいへ」



